あのとき、別の言葉をかけられたのではないかという思いと一緒に
本当は、あのときこんなふうに声をかけたらよかったのではないか。
もっと違う関係性を築けたのではないか。
この絵本を前にすると、そんな思いが何度も浮かびます。
『ひとりひとりのやさしさ』に出会ったのは、10年以上前でした。
読み終えたあと、登場人物の行動そのものよりも、言えなかった言葉や、しなかった選択のほうが強く残りました。
その残り方が、自分自身の過去と重なってしまう。
だからこの本は、ただ「いいお話」として棚に収めることができず、自分の中でも、どこか引っかかったままになっていました。
子どもが読んだら、どんなふうに受けとめるのだろうと思って
この絵本の舞台は小学校。子どもが読んだらどう感じるのだろう。
とくに、物語の結末をどんな言葉で受け取るのだろう。
そんなことを考えながら、さりげなく本棚に置いていました。
ある日、中学生の娘がその本を手に取り、読み始めました。
途中でやめることもなく、最後まで読み終え、少し間をおいて、こう言いました。
「結末が悲しすぎる」
その言葉は、とても率直で、同時に、こちらが軽く受け止めていいものではないと感じさせる響きがありました。
物語の最後にたどり着いたことが、その一言で十分に伝わってきました。
「本当にそうだね」と言って黙ったことは、正しかったのか
私は「本当にそうだね」とだけ返しました。
それ以上の言葉が出てきませんでした。
もっと言葉を添えることもできたはずです。
話を広げることも、気持ちを整理する手助けをすることも、もしかしたら必要だったのかもしれません。
あの沈黙は、寄り添いだったのか、それとも、何もできなかっただけだったのか。
傷つけてしまった可能性はなかったのか。
その問いは消えずに残っています。
改めてこの絵本を読み返しても、やはり同じところで立ち止まり、あのときと同じように、簡単には言葉にできません。
絵本紹介
『ひとりひとりのやさしさ』
文:ジャクリーン・ウッドソン
絵:E.B.ルイス
訳:さくま ゆみこ
出版社:BL出版
この絵本は、小学校の教室を舞台に、クラスの中で起こる子ども同士の関係を描いた絵本です。物語は、クラスの一員であるひとりの子どもの視点から進み、新しくやってきた子との出会いをきっかけに、友だちとの距離や集団の空気が少しずつ変わっていく様子が描かれていきます。声をかける場面、かけないまま過ぎていく時間、仲間の輪の中と外といった日常のやりとりが重なり、教室の中に緊張や対立が生まれていく過程が、時間の流れに沿って示されていきます。
物語の途中で、担任の先生が、池に小石を投げ入れる話を子どもたちに語る場面が置かれています。水面に落ちた小石から波紋が広がっていく様子が描かれ、その出来事も、教室で過ごす一日の中の一場面として描写されています。教室の時間はそのまま続き、子どもたちはそれぞれの立場で日々を過ごしていきます。
教室の中での立ち位置や視線の向き、友だちとの並び方は、文章だけでなく絵の中にも描かれ、クラスという集団の中で起きていることが、場面ごとに積み重なっていきます。学校生活の流れの中で関係が動いていく様子が、最後まで一貫して描かれています。
おすすめの理由
人との関係を、少し離れた場所から見直せる
ひとりひとりのやさしさは、人と人との間で起きることを、近すぎず遠すぎない距離で描いています。
誰かの立場に強く感情移入するというより、「関係そのもの」を見渡すような読み心地があります。
その距離が、日常の人間関係を考えるときの視野を、少し広げてくれます。
「気づく」という行為そのものに価値を置いている
この絵本は、行動の成功や失敗よりも、あとから訪れる「気づき」に光が当たっています。
何かをやり直せなくても、自分の中で見え方が変わることはある。
そのことが、静かに肯定されているように感じます。
やさしさを、完璧でなくていいものとして捉え直せる
やさしさは、いつも正しい形で現れるわけではありません。
迷ったり、ためらったり、間に合わなかったりする中にも、確かに存在しているものだと、この絵本は示します。
だから読後、「次はこうしなければ」と構えるのではなく、人と関わるときの肩の力が、少し抜けるような感覚が残ります。
まとめ
『ひとりひとりのやさしさ』は、答えを用意せずに、立ち止まる時間を残してくれる絵本です。
関係の中で起きたことを、すぐに整えなくてもいい。
見え方が変わるだけで、受け取り方が変わることもある。
やさしさを、完成形でなく途中のまま見つめられる。
思春期の揺れにも、大人の迷いにも、同じ距離で寄り添います。
読後、世界が少し違って見える。
そんな静かな前向きさが、手元に残ります。

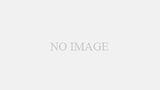

コメント